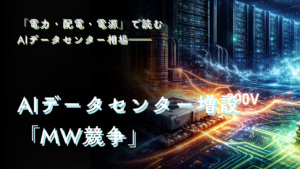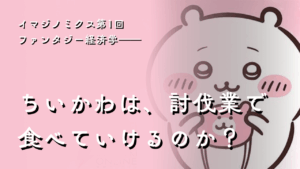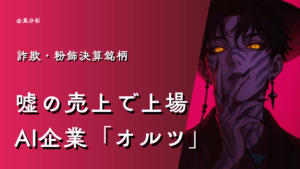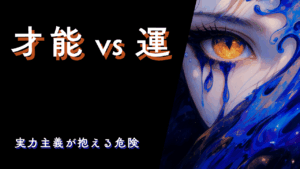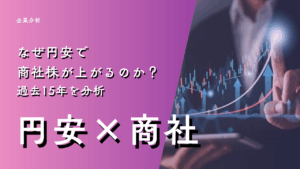こんにちは。
今日は「円高と円安って何?」について、分かりやすく説明します。
経済の基本用語として、円高と円安はよく聞きますが、具体的に何を意味するのかを理解しておくと便利です。この記事では、円高と円安の基礎知識と、簡単に覚えられる方法を解説します。
まず結論からお伝えします。
円高と円安は「円の価値」と考えると分かりやすいです。
例えば、1ドル100円でドルに両替できるとします。これが1ドル120円になると、100円で買えていた1ドルが120円出さないと買えなくなるので、円の価値が下がった、つまり円安と言えます。逆に、1ドル80円で買えるなら、円の価値が上がったので円高と言えます。
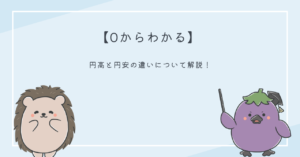
円高と円安の仕組み
それでは、円高と円安の仕組みについて詳しく解説していきます。
為替レートの変動
為替相場(為替レート)とは、外国為替市場において異なる通貨が交換(売買)される際の交換比率のことです。例えば、日本円とアメリカドルを交換する際の比率が為替相場となります。
もっと簡単にいうと、現金でやりとりせずに支払いを行うための方法が「為替」です。海外の映画などでよく登場するアイテム「小切手」。この小切手も為替の一種です。他にも、証書や手形、現代では銀行振り込みやキャッシュレス決済などが為替取引の一部です。
為替レートは基本的に需要と供給によって変動します。例えば、アメリカのドル(USD)と日本の円(JPY)の両替レートは日々変動しています。
この変動は、世界中の経済状況や市場の動向によって影響を受けます。

発達したのは江戸時代!? 「為替」のはじまりと現在
「為替」の歴史は非常に古く、日本では江戸時代に大きく発達したといわれています。
例えば、江戸の商人が大阪の商人に代金を支払う場合を考えてみましょう。現金を直接届けるのは盗難の危険があります。そこで、江戸の商人は両替商に代金を渡し、為替手形(支払いを依頼した証書)を発行してもらいます。この手形を受け取った大阪の商人は、指定の両替商に持って行き、代金を受け取ることができました。
このように、為替は売買代金の受け渡しや資金の移動を現金の輸送なしで行う手段です。
時代が進み、インターネットが発達した現在では、支払いや送金のために銀行振込や公共料金の銀行口座からの引落しなどが簡単にできるようになりました。直接現金を送ることや渡すことが少なくなったのです。
しかし、振込や口座振替も、実は為替取引の一種なのです。このように、国内で行われる為替取引は「内国為替」と呼ばれます。
円高と円安の例
例えば、1ドル100円で両替できるとします。
ある日、円の価値が下がって1ドルが120円必要になると、円安になったと言えます。反対に、1ドル80円で両替できるようになると、円高になったと言えます。
円高の例:
- 以前:1ドル = 100円
- 今:1ドル = 80円
- 結果:円の価値が上がり、円高
円安の例:
- 以前:1ドル = 100円
- 今:1ドル = 120円
- 結果:円の価値が下がり、円安
通貨の価格はどう決まる?
通貨の価格は、欲しいと思う人が多ければ多いほど、つまり需要が高まるほど高くなります。
逆に、需要が減少すれば、通貨の価値は低くなります。これは、私たちが日常生活で経験する「需要と供給の法則」と同じです。
例えば、人気の商品が多くの人に欲しがられると価格が上がるのと同じように、通貨も需要が高まれば価値が上がります。
円高のメリット
「円高」と聞くと、直感的に「円高の時に輸入商品を買うと高くなる」と感じる人もいるかもしれません。しかし、実際には逆です。「円高の時に輸入商品を買った方が安い」と覚えておきましょう。
例えば、1ドルが100円の時に100ドルの商品を買うと1万円(100円 × 100ドル)かかります。
しかし、円高が進んで1ドルが80円になると、同じ100ドルの商品が8000円(80円 × 100ドル)で購入できるのです。このように、円高になると輸入品の価格が下がり、安く買えるようになります。
また日本から他国へ海外旅行をするのにも、旅行費が安くなるでしょう。
その代わり、日本で作られ海外に輸出している商品が割高になるので、輸出産業が鈍化したり、海外から日本に来る観光客が減り、観光産業にも影響することが考えられます。
円安のメリット・デメリット
一方で、「円安」の場合は、円の価値が下がるため、輸入品が高くなります。
例えば、1ドルが100円の時に100ドルの商品を買うと1万円かかりますが、円安が進んで1ドルが120円になると、同じ商品を買うのに12000円(120円 × 100ドル)かかるようになります。
しかし、一方、円安になると、日本からの輸出が有利になります。例えば、100円の商品が1ドルで売れる場合、円安で1ドル120円になると、120円の売上が得られます。海外相手に輸出をしている主に日本の大企業にとってはメリットが多かったりもします。
為替の変動要因
為替レートの変動にはさまざまな要因がありますが、基本は需要と供給の関係です。
例えば、2013年から2015年頃には、日本銀行による大規模な金融緩和が行われ、日本円が大量に市場に出回ったため円安が進行しました。
また、2016年にはアメリカの利上げ期待の後退などで、米ドルを買う人が減り、日本円を買う人が増えたため、円高が進行しました。


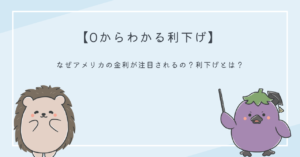
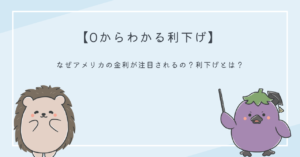
円安・円高が起きる要因
円安や円高はどのような要因で発生するのでしょうか?その発生の要因について、詳しく解説します。
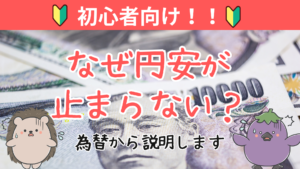
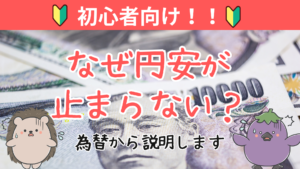
円安・円高を招く要因は、短期的に影響を与えるものと、中長期的に影響を与えるものの2種類に分けられます。
短期的な要因
まずは、短期的な要因について説明します。
中央銀行の為替介入
為替介入とは、中央銀行(日本では日本銀行)が外国為替市場で通貨の売買を行うことを指します。各国の中央銀行は、自国の通貨が高すぎたり安すぎたりするのを避けるために、為替相場に大きな変動が起こった際に介入することがあります。これにより、為替相場が安定するよう調整します。
その他の要因
政府要人の発言や市場予測とは異なる経済指標の発表なども、短期的な為替相場の変動要因となります。例えば、政府の高官が経済についてコメントしたり、予想外の経済データが発表されたりすると、市場の反応で為替相場が変動します。
中長期的な要因
次に、中期的な要因について説明します。
海外との金利差
一般的に、金利が高い国の通貨は上昇し、金利が低い国の通貨は下落します。金利が高い通貨を持つことで、より多くの利息を得たい人がその通貨を買うため、通貨の価値が上がります。
輸出と輸入
例えば、日本から何かを輸出した際、その代金をドルで受け取ることがあります。そのドルを日本円に換えるためにドルを売り、日本円を買うことで日本円の需要が高まり、円高になります。逆に、輸入が増えるとドルを買うために日本円を売ることになり、円安になります。
物価の変動
もし日本でインフレ(物価の上昇)が続き、海外でデフレ(物価の下落)が続いた場合、相対的に円の価値が下がり円安となります。逆に、海外でインフレが進行し、日本でデフレが続くと円高になります。
2022年から2023年にかけての円安進行の背景
では、2022年から2023年にかけて円安が進行した背景にはどういうことが挙げられるのでしょうか。
日本とアメリカの金利差の拡大
2022年から2023年にかけて、アメリカの中央銀行であるFRB(Federal Reserve Board)は物価上昇を抑えるために政策金利を引き上げていました。
一方、日本銀行はマイナス金利や大規模な金融緩和を続けていたため、日米の金利差が拡大しました。この金利差の拡大が、円安を引き起こしたと考えられます。
地政学リスク
ロシアによるウクライナ侵攻や台湾有事、北朝鮮のミサイル発射など、日本を取り巻く地政学リスクも円安の要因の一つです。これらのリスクが高まると、安全資産とされるドルに資金が流れ、円安が進行します。
まとめ 円高と円安
円高と円安の違いを理解することは、経済の基本を知る上で非常に重要です。円高は円の価値が上がることで、輸入が安くなり、海外旅行が有利になります。円安は円の価値が下がることで、輸出が有利になり、海外での利益が増えます。
為替レートの変動は、需要と供給の関係によって日々変わります。ニュースなどで円高や円安の話題が出てきたときは、ぜひ今回の記事を思い出してみてください。