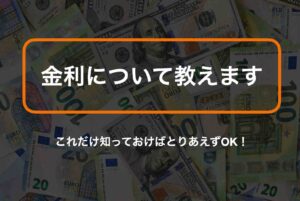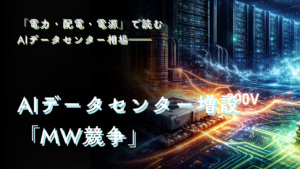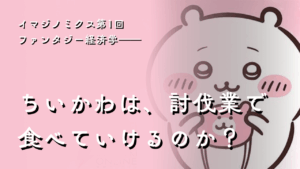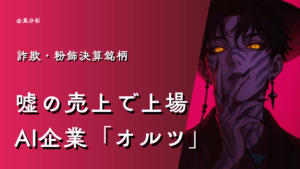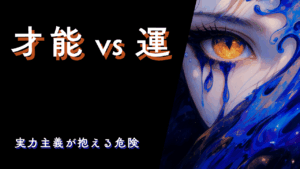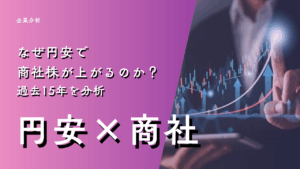はい、どうもこんにちは。
今日は、金利についてお話しします。
金利という言葉は皆さん聞いたことがあると思いますが、金利は金融知識の中でも一番避けられたり、面倒だと感じられる分野の一つです。
しかし、この知識がないと新聞や重要なニュースが理解できないこともあります。さらに、投資や車の購入、住宅の購入など、日常生活にも影響を与える重要な要素でもあります。
今回は初心者向けに、難しい話は抜きにして、一般の方々が知っておくべき金利についてお話しします。
金利についてこれだけは知っておこう
金利について話そうと思いますが、これは要するにお金を貸す際の手数料です。ざっくりと覚えておきましょう。ざっくりですざっくり。
自分がお金を貸す場合、金利が高い方が収益が上がります。一般的に、お金を貸す方法として銀行預金や債券があります。銀行預金は、お金を銀行に預けて金利を得るものです。金利が高ければ、毎年の利子も多くもらえるでしょう。これが金利が高いイメージです。
一方、お金を借りる際は、金利が低い方が支払いが少なくて済みます。一般的な人々がお金を借りるのは、住宅ローン、車を買うためのローン、またはカードローンの3つのパターンがあります。自分がお金を貸す立場と、お金を借りる立場とでは、金利に対する考え方がまったく異なります。
これは誰にでも聞いたことのある話で、今の60歳や65歳の世代では、昔は銀行預金の金利が高く、年間5%ほどの利子がついていた時代があったという話をする人がいます。しかし、これは人によるもので、確かに金利が高くて銀行にお金を預けていても、住宅ローンの金利が非常に高かった時代でもありました。
つまり、3000万円のローンを組んで最終的には6000万円支払うこともよくあったのです。したがって、自分がどちらの立場にいるかによって、金利に対する考え方が大きく異なるということです。

金利はどこが決めてるの?
金利についてより詳しくお話ししましょう。
金利は国が設定する要素であり、毎日変動しますが、基本的に国が決定します。銀行は国の指示に基づいて普通預金などの金利を設定しますが、銀行間で競争があるため、金利は異なることがあります。例えば、ある銀行が住宅ローンの固定金利を1.5%に設定しようと思っても、競合銀行が1.4%で提供している場合、競争力を持たせるために1.3%に設定し直すこともあります。
金利は国によって決定されますが、その背後にはいくつかの要因があります。一般的に、「国が景気を刺激したい場合、金利を引き下げます」という方針が採られます。日本の現在の状況でも金利は非常に低い水準にあり、国は低金利を維持し、国民に支出を促進させ、経済を刺激しようとしています。
一方で、景気を抑制したい場合、国は金利を引き上げる方向に進むことがあります。金利を引き上げると、お金を借りることが難しくなり、支出が減少します。これにより、インフレーションを抑制し、経済の成長を制限しようとします。国民が過度に借金をしている場合、国は金利を引き上げ、支出を抑制しようとします。
また、将来の景気に備えて金利を調整することもあります。現在好調な経済状況でも、将来の不確実性に備えて金利を引き上げることで、将来の景気変動に備えるカードを持つことができます。これは、営業マンが将来のビジネスの見通しを考えて、今の案件を保留するようなイメージと似ています。したがって、金利政策は将来の景気変動に対する備えとしても機能します。
日本では長らく低金利政策が続いており、その割には景気回復が思うように進んでいないため、今後も金利を引き上げる可能性は低いと考えられています。

「固定金利」と「変動金利」について違いを説明できますか?
住宅ローンや保険商品に関連する、一般の方々が知っておくべき重要な知識には、「固定金利」と「変動金利」があります。これらの知識は、住宅ローンや保険商品に関する選択をする際に役立ちます。
まず、住宅ローンにおいて固定金利とは、契約時点で金利が確定し、返済期間中に金利が変動することはありません。つまり、契約した時点で支払い金額が確定する仕組みです。将来の金利変動に左右されず、安定感があります。
一方、変動金利は、契約時の金利が比較的低く設定され、将来の金利変動に影響を受けて返済金額が変動する仕組みです。これにより、初期の返済額は低く抑えられますが、将来の金利上昇に伴い、返済額が増加する可能性があります。
また、これらの金利タイプは住宅ローンに限らず、保険商品にも適用されます。特に、積み立て型の保険商品では、金利が固定されている場合と、将来の金利変動に影響される変動金利型が存在します。通常、固定金利型が一般的ですが、変動金利型も提供されています。
このような選択肢があることで、将来の返済額やリターンがどのように影響を受けるかが異なります。したがって、契約時に金利が固定されるのか、それとも将来の金利変動に影響されるのかを理解し、自身の状況やリスク許容度に合った選択をすることが重要です。
金利と株価の関係についてこれだけは知っておきましょう!
金利と株価の関係について、一般の方々が理解すべきポイントについてお話ししましょう。
おそらく、新聞やニュースで長期金利の上昇が株価に与える影響について聞いたことがあるかもしれません。簡単に言えば、金利が下がると株価が上がり、金利が上がると株価が下がります。これは教科書的な基本原則です。
では、なぜこのような関係が存在するのでしょうか。例えば、皆さんが銀行にお金を預けても利益がほとんど生まれない状況を考えてみましょう。しかし、もし銀行預金の利率が突然5%に引き上げられるとしたら、多くの人が株式市場から資金を引き揚げて銀行に預けるでしょう。なぜなら、株式市場でのリスクを背負わずに確実に5%の利益が得られるからです。つまり、安定的なリタイアメントに役立つであろう銀行預金に資金が移動します。
逆に、金利が下がると、銀行預金にお金を預けてもほとんど利益が得られなくなります。その場合、多くの投資家はリスクを取って株式市場に投資する可能性が高まります。株価は投資家の需要によって影響を受け、需要が高まると株価が上がるという仕組みです。
このように、金利と株価は反比例の関係にあり、教科書的な理論に基づいています。したがって、金利の動向を把握することは、株式市場での投資判断において重要です。
金利が上がってもと株価が下がらないこともある?
しかし、実際の現場では、教科書通りの理論が必ずしも当てはまらないことが多いことがあります。
数年前にアメリカで長期金利がわずかに上昇する可能性があるというニュースがありました。このとき、多くの人々はアメリカの長期金利が上昇すると、株価が急落する可能性があるのではないかと心配し、株を売却して預金に回すか、債券を購入することを考えるようになりました。しかし、実際には株価は急落しませんでした。この出来事が示すように、教科書通りの金利が上昇すれば株価が下がるという一般的な理論が必ずしも当てはまらない場合があることを考える必要があります。
この出来事の背後には、アメリカ経済が強調され、金利を引き上げる余裕があるという見方が影響しています。アメリカ経済が好調で企業が収益を上げているという状況では、多くの投資家が株式市場に自信を持ち、株を購入しようとする傾向があります。このように、市場は教科書通りの理論に従わないことがあり、株価の動向は多くの要因に影響されることを理解しておく必要があります。株価は捉え方によって異なるため、一概に教科書通りに予測することは難しいと言えます。

金利についてのまとめ
金利は経済と個人の財政に深い影響を与える重要な要素です。以下に、金利の主なポイントをまとめました。
- 金利の種類:
- 固定金利: 契約時の金利が一定期間変わらないタイプ。
- 変動金利: 金利が変動する可能性があるタイプ。
- 金利と株価の関係:
- 一般的な理論では、金利が上昇すれば株価は下落し、金利が低下すれば株価は上昇するとされています。
- ただし、実際の市場ではこの理論が必ずしも当てはまらないことがあります。市場は様々な要因に影響されます。
- 国の金利政策:
- 国は金利政策を通じて経済を調整しようとします。金利を引き下げると、経済を刺激し、支出を促進しようとします。
- 金利を引き上げると、支出を制限し、インフレーションを抑制しようとします。
- 金利と個人財政:
- 金利は住宅ローン、クレジットカード、積み立て保険などの金融取引に影響を与えます。
- 低金利時には借金がしやすくなり、高金利時には借金が難しくなります。
- 市場の複雑さ:
- 金利の動向は市場の複雑な要因によって影響を受けるため、予測が難しいことがあります。
- 投資や財政計画を立てる際には、金利変動の影響を考慮に入れることが重要です。
金利は個人の資産と経済全体に大きな影響を及ぼすため、金融情報を注意深く監視し、適切に対処することが賢明です。