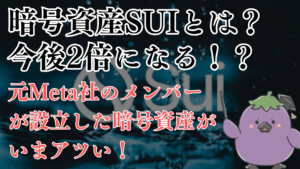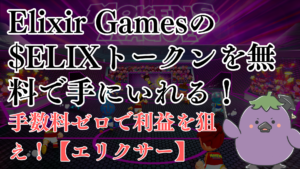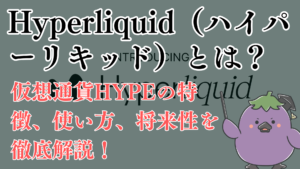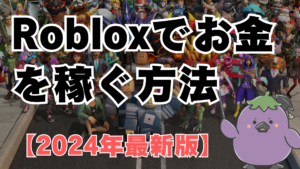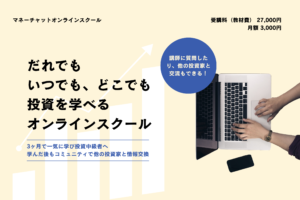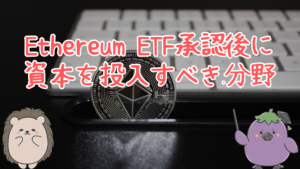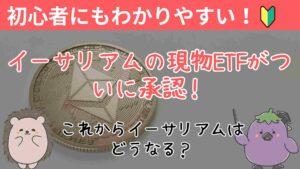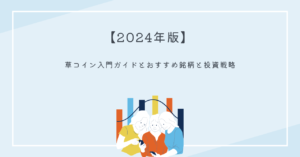仮想通貨の人気が高まり、特にビットコインは過去最高値を記録しました。
しかし、多くの投資家が気づかない「課税の落とし穴」が存在します。この問題を理解し、適切に対策を講じることで、大きな損失を回避できます。本記事では、初心者でもわかりやすく、仮想通貨に関する課税制度とそのリスクについて解説します。

※この記事には広告が含まれるのだ!
仮想通貨の課税仕組みとは?
仮想通貨を売却して利益を得た場合、その利益は「雑所得」として扱われ、最大55%(所得税45%+住民税10%)の課税対象となります。例えば、400万円で購入したビットコインが1億円になった場合、利益の9,960万円に対して課税されます。
- 取得価格:400万円
- 売却価格:1億円
- 利益:9,960万円
- 税額:約5.5億円(利益の55%)
仮想通貨を相続すると、その評価額に基づいて相続税が課されます。最高税率は55%であり、多額の税金を10か月以内に現金で納付する必要があります。
仮想通貨の取引で得た利益は、原則として「雑所得」に分類
雑所得に分類される所得の合計額の収入すべき時期は、その収入の種類に応じて、他の所得の合計額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日を含めた年分となっています。
会社員など一社から給与所得を得ている方は、利益が20万円を超える場合に確定申告が必要です(主婦や学生など扶養されている方は33万円以上)。
雑所得とは?
雑所得は、国税庁が定める所得の10種類の中で、どの所得分類にも該当しない収入を指します。国税庁のホームページでは、雑所得を以下のように定義しています。
「雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいう。」
雑所得の具体例としては、以下のような収入が挙げられます。
- 公的年金等(年金受給額)
- 副業収入(原稿料、講演料、フリマアプリの販売収益など)
- 非営業用貸付金の利子
- シェアリングエコノミーに関連する収入(民泊、配車サービスなど)
雑所得の特徴
- 総合課税
雑所得は総合課税の対象であり、他の所得(給与や事業所得など)と合算して課税されます。そのため、所得が増えるほど高い税率(最大55%)が適用される可能性があります。 - 計算方法
雑所得は以下の式で算出します。
雑所得 = 収入金額 – 必要経費
必要経費とは、その収入を得るためにかかった費用(交通費、備品購入費など)です。 - 仮想通貨の場合
仮想通貨の売却益や取引による収入も雑所得に該当します。仮想通貨の課税が厳しいと言われる理由は、この雑所得として扱われることで高い税率が適用されるためです。
雑所得の具体例:仮想通貨の場合
例えば、ビットコインを1BTC=100万円で購入し、その後1BTC=500万円で売却した場合、以下のように計算されます。
- 売却額:500万円
- 購入額(取得費):100万円
- 利益:500万円 – 100万円 = 400万円
この400万円が雑所得として課税対象となります。所得が増えるほど累進税率により課税額が増加するため、高額な税金負担が生じる可能性があります。
仮想通貨に特有のリスク
仮想通貨は売却時の所得税と相続税が同時に課される可能性があります。相続後に仮想通貨を売却すると、さらに売却益に課税されるため、大幅な損失や自己破産に陥る危険性があります。
16億円相当のビットコインを相続
- 相続税:約8.8億円
- 売却後の税金:約5.5億円
- 合計課税額:約14.3億円 → 実質的に現金が不足
仮想通貨の価値が高騰しても、現金化しない限り税金は支払えません。また、相続や売却後の税金が重く、最終的に自己破産に至るケースも考えられます。
対策:どうすればリスクを軽減できるのか?
では、どのように仮想通貨で税金対策をすればいいのでしょうか?
1. 早めの現金化
まずは、利益が出た段階で一部を売却し、課税対象の金額を分散させることで税負担を軽減できます。これを「ドルコスト平均法」の考え方で行うと、リスクを分散できます。
2. 法人を活用する
個人ではなく法人を設立して仮想通貨を保有すると、法人税(約33%)の適用を受けられます。さらに、法人内で利益を活用することで、税負担を最小限に抑えることが可能です。
3. 税制改正の動向に注目
現在、仮想通貨の課税制度を「総合課税」から「分離課税」(20%前後)に変更する提案がなされています。特に国民民主党から自民党に提案がおこなれています。税制改正が行われた場合、税負担が大幅に軽減される可能性があります。



ただ、自民党は今のところ全く聞く耳を持っていないようなのだ……
仮想通貨税制改正について
仮想通貨(暗号資産)取引は、利益が大きくなる可能性を秘めていますが、その反面、税金に関する課題も少なくありません。
1. 総合課税から分離課税への変更
現在、仮想通貨取引による所得は「総合課税」として扱われ、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税が適用されています。この仕組みでは、最大55%(所得税45%+住民税10%)もの税金が課されることがあります。
要望書では、この制度を「分離課税」へ変更することが求められています。分離課税が導入されれば、税率は一律20.315%(所得税+住民税)となり、以下のような効果が期待できます。



つまり、株と同じにしようという提案なのだ!
会社員で年収433万円、仮想通貨の所得が100万円の場合を例に考えます。
- 総合課税(現行制度)
税金合計:約117.1万円 - 分離課税(改正後)
税金合計:約64.2万円
節約額:約52.9万円
分離課税が導入されれば、大幅な税負担軽減が可能です!
2. 仮想通貨の損失繰越制度の導入
株式やFX取引では、損失を翌年以降に繰り越して利益と相殺できる「損失繰越制度」があります。しかし、現状では仮想通貨取引にはこの制度が適用されていません。
- 税負担の軽減:損失がある年の翌年以降の利益と相殺でき、税金が減少。
- 長期的な投資を支援:ボラティリティ(価格変動)の高い仮想通貨市場において、安定した資産形成をサポート。
例えば、2025年に100万円の損失が発生し、翌年に150万円の利益が出た場合、50万円にのみ課税されるため、税負担が大きく軽減されます。
3. 暗号資産同士の交換における課税の見直し
現在、暗号資産同士の交換も課税対象とされています。たとえば、ビットコインをイーサリアムに交換した場合、その時点での時価で利益が計算され、課税が発生します。これにより、以下のような問題が生じています。
現行制度の課題
- 資金の流動性不足:実際に法定通貨で利益を得ていなくても課税される。
- 税計算の複雑化:交換のたびに損益を計算する必要がある。
改正案のポイント
- 交換を非課税に:一定の条件下で暗号資産同士の交換を非課税または課税繰り延べとする提案。
- メリット:個人投資家が多様な暗号資産運用を試みやすくなる。
- 注意点:制度設計によっては税計算がさらに複雑化する可能性も。
仮想通貨初心者へのアドバイス
右も左もわからないという仮想通貨初心者の方へのアドバイスをまとめました。
- 知識をつける
税金に関する基本知識を身につけることは、仮想通貨投資の成功に欠かせません。 - 専門家に相談
税理士やファイナンシャルプランナーに相談し、適切な節税対策を講じることをおすすめします。 - 小額から始める
リスクを抑えるため、初めは少額の投資から始めるのが良いでしょう。
マネーチャットでは、投資や仮想通貨初心者のためのコミュニティを運営しています。わからないことは質問し放題ですよ!
マネーチャットでは、超初心者から中級者の方にぴったりな投資の学校を運営しています。毎週の動画学習に加え、毎日の経済解説、そしてみんなと一緒に学習したり意見交換したりする場を作っています。
とりあえず無料で1ヶ月やってみよう! =>
https://community.camp-fire.jp/projects/view/760550#menu
まとめ 2025年最新版 仮想通貨の税金
仮想通貨は魅力的な投資先ですが、課税リスクを正しく理解しないと大きな損失を被る可能性があります。特に、相続や売却時の税金には注意が必要です。早めの現金化や法人活用などの対策を取りつつ、税制改正の動向を注視することで、リスクを軽減しながら利益を最大化しましょう。
無料LINEグループでも意見交換していますので、ぜひご参加ください!
マネーチャットでは、投資の超初心者から中級者の方が一緒に意見や情報交換したり、研究するグループを運営しています!
一緒に株や資産運用、経済について語ろう!
https://line.me/ti/g2/3-2hZJtrzPp5Lidg7F_Qgr2aS4lCj9hZcBelEg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default