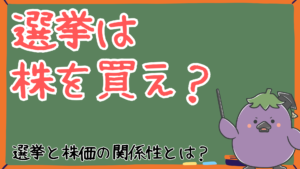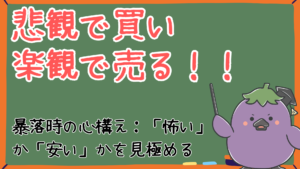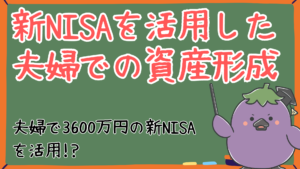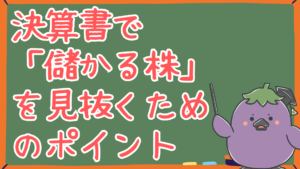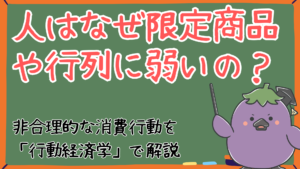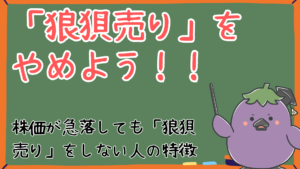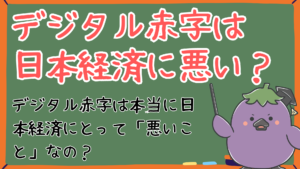「ナッジ理論」という言葉を聞いたことはありますか?
ナッジ理論とは、人間の心理に基づき近年アメリカで生まれた行動経済学の理論のことを指します。
ナッジとは、英語で「nudge」と書きます。この単語には「ゆっくりと動かす」「近づく」「優しく説得する」という意味があります。
ナッジ理論とは、
あくまで個人には選択の自由を残しつつ、いろいろな選択肢を提示するときに、その個人にとって最も良いと思われる選択肢が選ばれやすいように、提示方法を工夫する
というものです。
人間の心理に基づき、さりげなくこちらにとって好ましい選択をしてもらうように促すため、マーケティングへも応用が可能です。
そこで今回は、ナッジ理論の詳細とマーケティングへの応用方法、成功事例について解説していきます!

ナッジ理論とは
ナッジ理論は2008年に、米国の経済学者のリチャード・セイラー教授と法学者のキャス・サンスティーン教授によって提唱されました。
経済学は、人は自制心が強く、常に自己利益の最大化のために合理的な行動をするということを前提としています。
しかし、本当に人間は常に合理的な行動をするのでしょうか?
あなたも学生時代、宿題になかなか手をつけられずに締め切り前になってやっと手をつける、ということがありませんでしたか?
やらなければと思いながらギリギリになってしまうのは怠け者だからではなく、「人は常に合理的判断に基づいて行動をする訳ではない」という人間の性質のせいなのです。
こういうある種「ダメ人間」ということを前提に考えられたのが行動経済学です。
頭ではわかっていても衝動買いなどをしてしまうのが人間です。
行動経済学は、心理学的要素を数理的にモデル化し、現実に合うように経済学の適用範囲を広げたものです。
ナッジ理論とは、
あくまで個人には選択の自由を残しつつ、いろいろな選択肢を提示するときに、その個人にとってより良い良いと思われる選択肢が選ばれやすいように、提示方法を工夫する
というものです。
ナッジ理論のフレームワーク|ナッジ理論とマーケティング
次に、ナッジ理論のフレームワークについて解説します。
イギリス政府がナッジ理論を活用する際、特に効果的であった施策のポイントを4つにまとめた「EAST」というフレームワークがあります。
ナッジ理論で重要な要素の頭文字から取られ「EAST」という名称が付けられています。
・Easy(簡単・簡潔)
シンプルなメッセージで伝える、面倒や手間をできるだけ少なく設計する。
例:アンケートで選ばせたい項目をデフォルトに設定しておく。
・Attractive
お金以外の報酬(インセンティブ)を用意する、ポイントなどを無料で与えて失効期限をつけるなどメリットを作る。
例:成果を見える化する。成果に応じて報酬が発生する。
・Social(社会性)
みんな同じことをしているという社会規範を示す。
例:人数制限を設けて、わざと行列を作る。
・Timely(タイムリー)
適切なタイミングで情報を提供する。
例:出産前後に生命保険を勧める。引越しした人に家具を勧める。
さて、個人に非合理的な側面があることを認めるとしても、その個人の意思決定や行動に他人が介入することは、好ましいのでしょうか?
個人の選択の自由をも守りつつ他者が介入すればいいの?|ナッジ理論
ナッジ理論とは、
あくまで個人には選択の自由を残しつつ、いろいろな選択肢を提示するときに、その個人にとってより良い良いと思われる選択肢が選ばれやすいように、提示方法を工夫する
というものということはわかっていただけたかと思います。
例えば、自分の資産運用の選択をする際に、コンサルタントが5種類の選択肢を提示してそれから自由に選ぶという方法があったとします。
しかし、5種類の選択肢は提示されるものの、本人が選択しない場合は、1番目がデフォルトで選ばれるというパターンもありますよね。
コンサルタントは最も推奨する運用をデフォルトに設定しておくことで、その選択肢へ誘導することもできます。そして、5種類の選択肢は提示されているので、資産保有者の選択の自由は守られます。
ナッジ理論の例|ナッジ理論をビジネスで活用する方法
ここでナッジ理論の例、ナッジ理論のマーケティングへの応用例を見ていきましょう。
ナッジ理論をビジネスで応用するためには、
デフォルトを選びやすい
社会規範を感じると、みんなと異なっている状態やマナーに欠ける行動に後ろめたさを感じる
「多くの人がそうしている」のような情報があると決断しやすくなる
がポイントです。
子供たちのカフェテリアでの陳列を変更する|ナッジ理論の例
デザートを最初に置くか、最後におくか、あるいは目線の高さに配置する食べ物をフライドポテトにする野菜スティックにするか、というのを悩んでるケースを想像してみましょう。
この場合、
メニューの陳列を変えただけで消費量が25%増減した食べ物があるのです。
つまり、メニューの陳列を決める人が消費者の行動を決定することができるということです。
では、どのようにメニューの陳列を決めれば良いのでしょうか?
- ランダムに陳列する
- 儲けを最大にするように陳列する
- 子供達にとって最も良いと思われる陳列にする
この場合、最後の「子供達にとって最も良いと思われる陳列にする」という陳列方法が最も個人に自由な選択の余地を残した上で、その人に最も良い選択肢が選ばれやすいようにしていると言えます。
ナッジ理論に基づいたポイント付与|ナッジ理論の例
マーケティングの一つとして顧客向けにポイントを付与している企業も多いと思います。
この時に「インセンティブ」と「デフォルト」のテクニックを用いるとその効果を上げることができます。
人は目標に近づくほど達成するために多くの努力を払うようになります。
例えば、スタンプ10個でコーヒーが一杯無料で飲めるカードは、スタンプが10個に近づくにつれて、来店頻度が上がるのです。
ここで、スタンプ10個でコーヒーが一杯無料ではなく、スタンプ12個で一杯無料と変更しましょう。
しかしそのとき、一番最初の時点で2個のスタンプが特別に押されているという形をとります。
つまり、デフォルトで2個のスタンプが押されているので、結果としてはスタンプ10個でコーヒーが一杯無料と変わりません。
どちらも必要なスタンプ数は同じですが、後者の方がゴールに向かって前進しているように感じら、コーヒーの購入頻度が高くなったという実験結果があるようです。
このようにデフォルトうまく設定することで、顧客の行動をある程度コントロールすることができます。
(出典:https://tosho-antenna.jp/entry/2021/01/21/110000)
ナッジ理論で階段を使いたくなるに!|ナッジ理論の例
駅構内やデパートなどでエスカレーターと階段があったとき、つい楽なエスカレーターを選びがちではないでしょうか。
そこで、階段に「ここまで登って〇〇カロリー」と表記したところ、階段を選ぶ人が増えたという事例があります。
エレベーターか階段のどちらを使うかは個人の自由ですが、これは健康促進のために階段を登りたくなる仕掛けをしたナッジ理論です。
顧客行動を変えるサイトデザイン
ナッジ理論はWebデザインでも使えます。
国連によるジェンダー平等のための社会連帯運動である”HeForShe”では、男性の参加を促すことが課題でした。
こちらを支援した行動デザインの専門コンサルティング会社によると、男性視点での行動の阻害要因は、「HeForSheを自分ごととして捉えにくい」「何をすればいいかわからない」「登録が面倒」の3点だと判明しました。
そこで、ウェブサイトに「I commit(参加します)」のフリップを掲げた男性の写真を多く載せ、世界中で参加を宣言した数を示すカウンターを掲載し、さらに「参加は無料、たった10秒で完了」の説明を追加した結果、参加者数が2%から24%に向上したようです
ナッジ理論を納税に活用!|ナッジ理論の例
イギリスでは納税率の低さが問題視されていました。
そこでイギリス政府は、税金滞納者に対して税金滞納者に「あなたが住んでいる地域のほとんどの人々は期限内に納税しています」という内容の手紙を送ったのです。
その結果、滞納者は社会的圧力を感じるようになり、納税率が68%から83%に増加しました。ナッジ理論の要素である「Social」がうまく機能した例と言えるでしょう。
社内の人間関係へのナッジ理論の活用方法|ナッジ理論と企業の応用
ナッジ理論は社内コミュニケーションを活性化するためにも活用できます。
目標を細分化する
コミュニケーションの「始め方」にルールを作る
フィードバックを行う
リマインドを行う
この四つがポイントとなります。
目標を細分化する
はじめから大きな目標の達成を目指そうとすると、コミュニケーションのハードルが高くなってしまいます。
目標を細分化することも重要です。
例えば、業務上のトレーニングでは、カリキュラムを細かいレベルに分割し、それを繰り返し行うように従業員に設定しましょう。
この場合では、従業員がレベルごとの課題や改善点に気付きやすくなり、結果的に素早くスキルアップをすることが可能になります。
達成しやすい目標を細かく設定することで、その都度コミュニケーションを取ることができます。
最終的なゴールを分割し、業務に取り組みやすく、コミュニケーションを取りやすい環境を整えるということも大切です。
コミュニケーションの「始め方」にルールを作る
ミーティングを行う際に、「最近どう?」「何か気になっていることある?」など曖昧な言葉だと答えにくくなります。
会話が弾まず、本来聞きたい内容にたどりつけないこともあるでしょう。
内容の濃いミーティングをするためには、「今悩んでいることはありますか?」「助けてもらいたいことはありますか?」など、会話の入りを決めるのがおすすめです。
質問がより具体的になることで、コミュニケーションがスムーズになるのです。
特にコミュニケーションに苦手意識がある方にとっては、最初の話題が決まっていることで、ストレスが軽減し、メンバーのことをより頻繁にチェックするモチベーションが生まれます。
フィードバックを行う
フィードバックを行うことは、ナッジ理論のフレームワークのうち、Attractiveに該当します。取り組みに対して評価したり、改善点を伝えたりすることで、自分自身を振り返り、成長を促すことができます。
Googleでは、マネージャーに対して半年に一度、彼らの強みと改善点をまとめたレポートを提供していたそうです。これによって、たとえ研修に参加していなくとも、多くのマネージャーが次の半年間に自分の弱みに向き合い、改善することができたといいます。
このような変化が起こるのは、多くの人が「成長したい」という気持ちを持っているからです。フィードバックを受けることで、人は自分自身の課題を自覚し、改善しようとします。
フィードバックをすること、それに対して会話をすることが日常的になれば、ほめることや指摘すること、意見を言うことなど、発言のハードルが下がり、コミュニケーションが活発になるのではないでしょうか。
リマインドを行う
タスクに対してリマインドを行うこともナッジのひとつです。
人の認知能力は限られています。「期日までにやるように」と一度指示しても、多くのタスクを抱える従業員にとっては、期日ギリギリになったり、締切を過ぎたりする可能性は往々にしてあります。
そこでリマインドによって期日を伝えたり、やってもらいたいことをこまめにお願いしたりすることで、タスクを強制するのではなく、何気なくタスクへの取り組みを促すことが効果的です。
ナッジ理論 まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、ナッジ理論について解説しました。仕組みは理解できても、すぐにナッジ理論をマーケティングに実践するのは難しいかもしれません。
ただ、ナッジ理論を利用すると、コントロールされている気がするという不快感を与えるかもしれないので、バランスは常に考える必要があります。