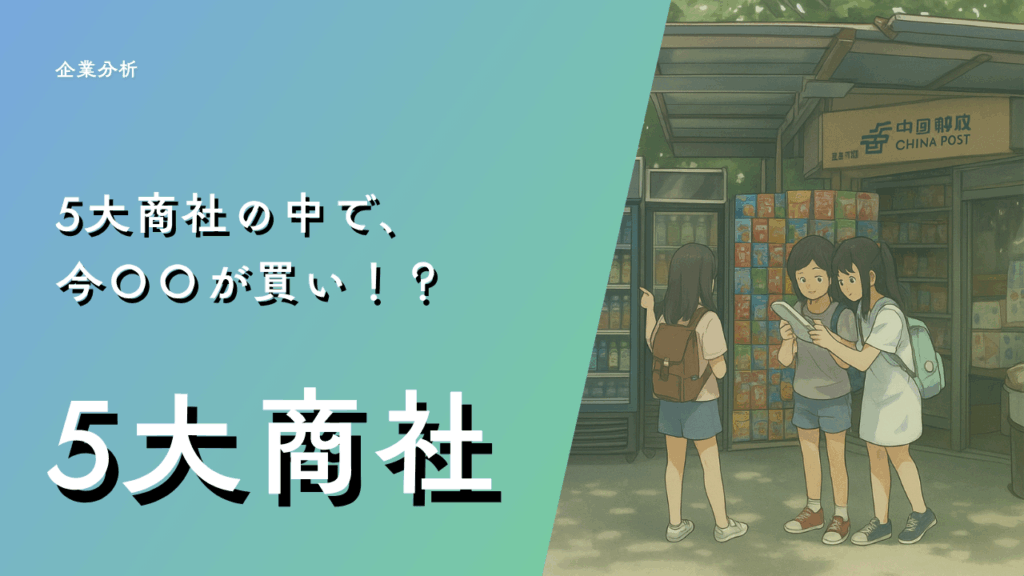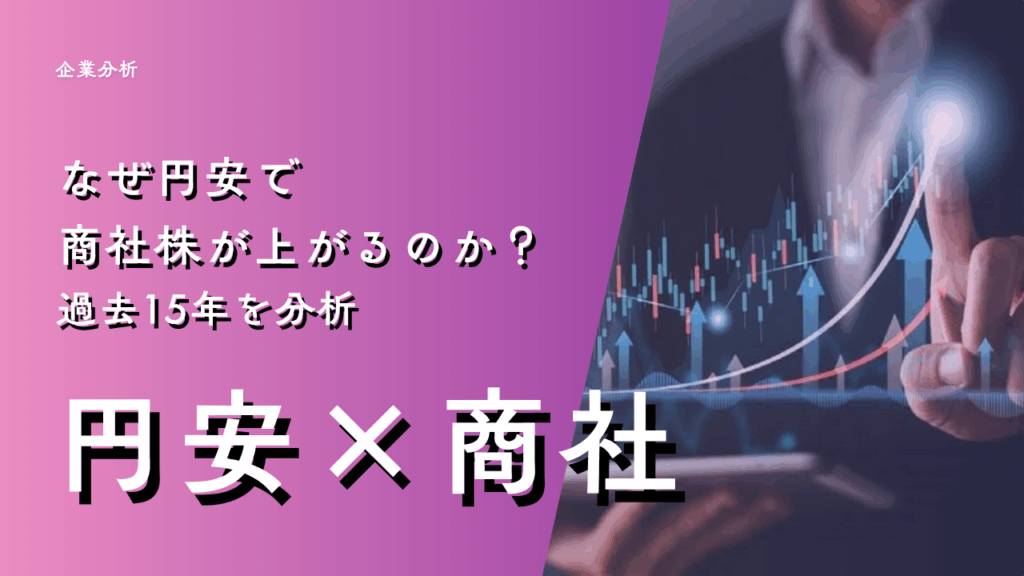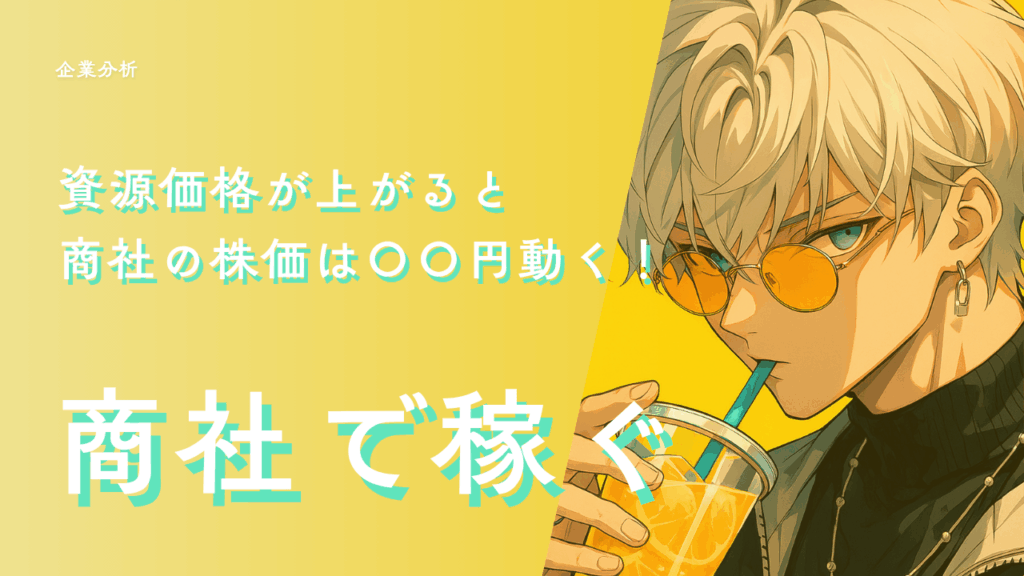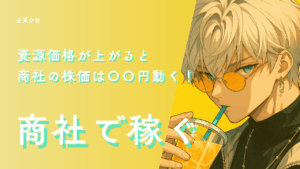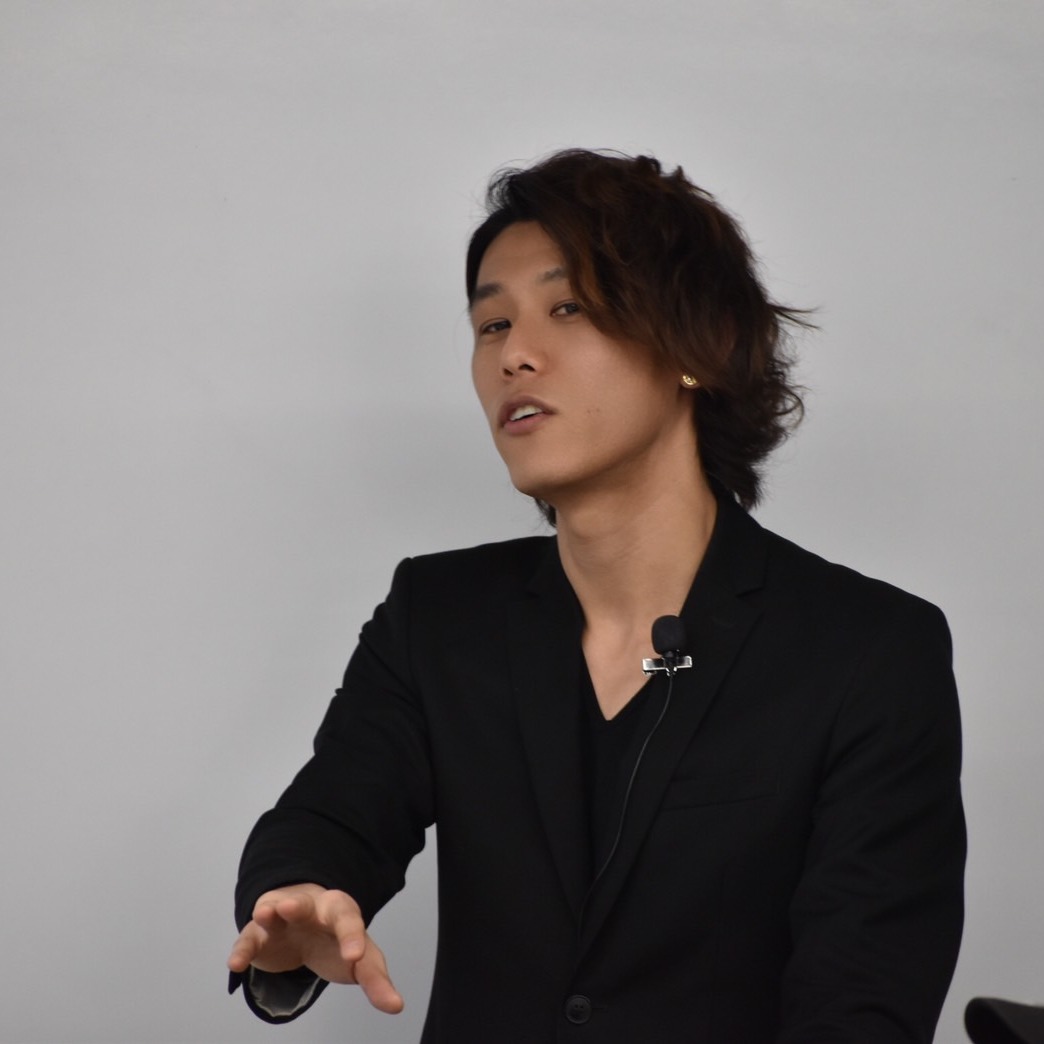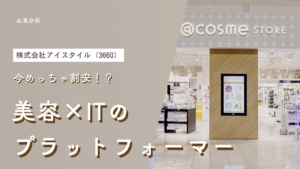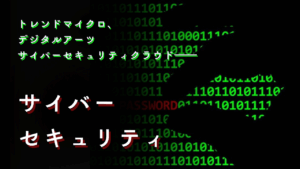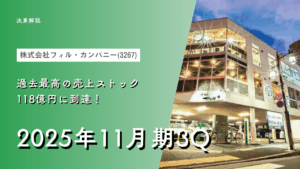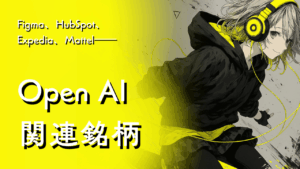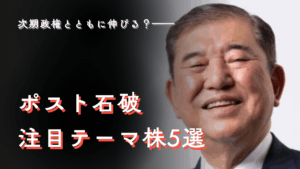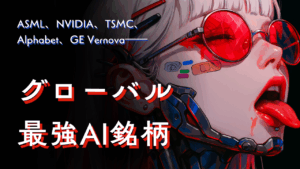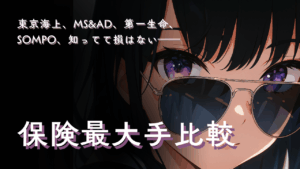「最近またドル円が150円に近づいてきた」
「商社株、また最高値更新らしい」
ニュースでよく見るけれど、どうして円安や資源高になると商社株が強いのか、仕組みをちゃんと説明できる人は少ないのではないでしょうか?
本記事では、この「なぜ?」に対し、データ×統計で実際にどれくらい反応しているのかを検証していきます。
また、5大商社のおすすめ銘柄は別記事で解説していますので、まだ読んでない方はぜひ先にそちらを読んで学習してみてください!
なにか質問や意見がある方は、ぜひ弊コミュニティでお会いしましょう!
マネーチャットでは、超初心者から中級者の方にぴったりな投資の学校を運営しています。毎週の動画学習に加え、毎日の経済解説、そしてみんなと一緒に学習したり意見交換したりする場を作っています。
とりあえず無料で1ヶ月やってみよう! =>
https://community.camp-fire.jp/projects/view/760550#menu


📌 商社株はなぜ為替や資源価格で動くのか?
「商社株は円安で上がる」
「原油が上がると三菱商事が上がる」
よく聞く話ですが、これはなぜでしょうか?
その理由は商社の収益構造にあります。
彼らは「資源を仕入れ→加工・販売」するだけでなく、海外鉱山・LNG権益などの投資事業を多数保有しています。
つまり、
- 売上:外貨建て
- 原材料:資源価格に連動
- 決算通貨:円
というマクロ感応度の高いビジネスなのです。
🔸 円安で得をする構造
商社が円安で得をする理由は単純です。
- ドル建てで得た利益 → 円換算で膨らむ
- 外貨建て資産 → 評価額が上昇する
このように、円安が直接、営業利益・経常利益に好影響を与える仕組みになっています。
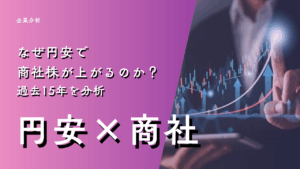
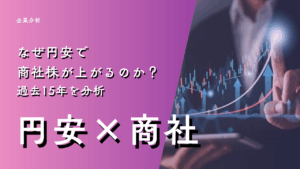
🔸 資源価格の影響も大きい
商社の多くが、たとえば以下のような資源権益を保有しています。
| 商社名 | 主な資源関連事業 |
|---|---|
| 三菱商事 | LNG、石炭、銅鉱山 |
| 三井物産 | 原料炭、鉄鉱石、天然ガス |
| 丸紅 | 銅、発電、アグリ |
| 住友商事 | 銅鉱山、石油開発 |
| 伊藤忠 | 食料・非資源系中心 |
特に、銅・原油・天然ガスの価格上昇は、保有プロジェクトの収益性に直結します。
そこで本記事では、
「円安・資源価格が、実際にどの程度、商社株価に影響を与えているか?」
という問いに対し、15年分の実データをもとに重回帰分析を行い、統計的に可視化しました。
その結果、各社の「資源感応度」がはっきりと見えてきたのです!
5大商社のビジネス構造と「資源感応度」の違い
商社株の価格は、円安や資源価格の変動によって動くことが多い。
これは定説ですが、「どの商社が、どの資源に、どれだけ影響を受けやすいのか?」はあまり語られていません。
本章では、5大総合商社の事業構造を比較しながら、資源価格への感応度の違いを定性的に整理していきます。
🏢 5大総合商社の事業構成
以下は、各商社の2023年3月期決算に基づく、ざっくりとしたセグメント別利益構成です。
| 企業名 | 資源セグメント比率 | 非資源セグメント比率 | 外貨収益比率(推定) |
|---|---|---|---|
| 三菱商事 | 約55%(天然ガス・金属) | 45%(食料、物流、金融) | 高い(70%以上) |
| 三井物産 | 約50%(鉄鉱石、原料炭) | 50%(自動車、医薬、食品) | 高い(65〜75%) |
| 伊藤忠商事 | 約25%(石炭など) | 75%(繊維、生活資材、食品) | 中程度(40〜60%) |
| 住友商事 | 約40%(銅、石油、鉱山) | 60%(交通、不動産、メディア) | 中〜高 |
| 丸紅 | 約35%(銅、発電など) | 65%(アグリ、商流、建機) | 中程度 |
三菱商事・三井物産:資源感応度が最も高い
- 海外資源権益(LNG、鉄鉱石、原料炭など)を豊富に保有
- 「資源価格 × 生産量」でダイレクトに利益が変動
- 為替や資源価格の変動を、ダイレクトに業績へ反映
📈 分析では、銅や原油との連動性が非常に高いことが確認されます。
伊藤忠商事:非資源型で円安・資源耐性がある
- 主力は繊維・生活資材・食品など、内需型ビジネスが中心
- 円建て売上・円建てコストが多く、「為替の影響」が相対的に小さい
- 穀物など商品価格の影響は受けるが、利益に直結しにくい構造
💡 投資家視点では、「円安・資源高の局面におけるディフェンシブ商社」として評価されやすい。
住友商事・丸紅:中間的なポジション
- 資源依存も一定程度あり、同時にインフラや不動産などの非資源セグメントも大きい
- 特定資源に偏らず、ポートフォリオ分散型
⚖️ 資源高で一定の追い風を受ける一方、過度なレバレッジ(依存)もないため、業績が比較的安定しやすい点も評価されるポイント。
👉 次章では、実際にこれらの違いが「株価と資源価格の相関」にどのように現れるか、15年分のデータを用いて検証していきます。
資源×為替×商社で稼ぐには? – 資源価格が1単位上がると商社の株価は〇〇円動く!?
※ ここから有料パートです。信頼できる分析の土台となる「データ設計」や「モデル構築」について、具体的に丁寧に解説していきます(ここからは、有料メンバー or 有料noteで閲覧できます)。